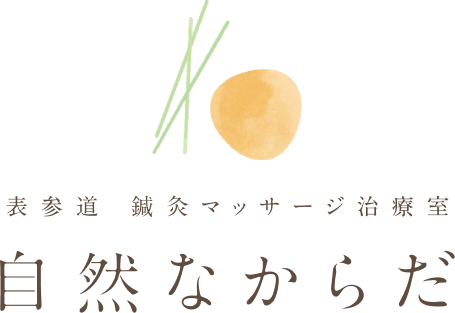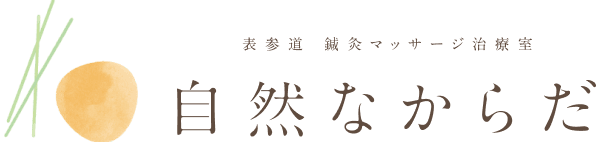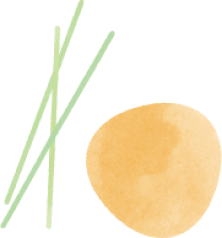新着情報

(1)自律神経とは?役割と乱れる原因をわかりやすく解説
ストレスと自律神経

●はじめに
「なんとなく体調が悪い」「検査では異常がないのに疲れやすい」――そんな経験はありませんか?
その不調の背景には、自律神経の乱れが関わっていることが多いのです。
今回は、自律神経の基本的な役割と、なぜ乱れてしまうのか、その原因について分かりやすく解説します。
●自律神経とは?
自律神経とは、私たちの意思とは無関係に働き、体をコントロールする神経です。心臓を動かしたり、呼吸を整えたり、体温を一定に保ったり――生きていくうえで欠かせない働きを担っています。
自律神経には大きく2つの種類があります。
交感神経:活動モード。主に日中や緊張時に働き、心拍数や血圧を上げ、体をシャキッとさせる
副交感神経:休息モード。主に夜やリラックス時に働き、体を休め、回復させる
この2つがバランスよく切り替わることで、心身は健康なリズムを保ちます。
●自律神経が乱れるとどうなる?
本来であれば「昼は活動」「夜は休息」と切り替わるはずの自律神経。ところが、このバランスが崩れると、次のような不調が現れやすくなります。
慢性的な疲労・だるさ
気分の落ち込み、イライラ、不安感
頭痛、肩こり、めまい
胃腸の不調(便秘・下痢・食欲不振)
冷えやほてり、体温調節の不安定さ
睡眠の質の低下(寝つきが悪い・眠りが浅い)
これらは「病院で検査をしても異常が見つからない不調」として現れることも多いため、「なんとなく不調」と表現されやすいのです。
●自律神経が乱れる主な原因
(1)ストレス
人間関係や仕事のプレッシャーが続くと、交感神経ばかりが優位になり、リラックスできなくなります。
(2)生活習慣の乱れ
睡眠不足や夜更かし、食生活の偏りは、自律神経の切り替えを妨げます。
(3)季節や環境の変化
季節の変わり目や気圧の変動は、自律神経の調整に大きな負担を与えます。
(3)加齢やホルモンバランスの変化
特に女性は更年期にホルモンと自律神経の両方が不安定になりやすく、不調が出やすい時期といえます。
●東洋医学から見た自律神経の乱れ
東洋医学では、自律神経の不調を「気血の巡りが滞る」「陰陽のバランスが崩れる」と捉えます。疲労や気分の乱れも体だけでなく心の巡りが関わっており、鍼灸はそのバランスを整える有効な手段とされています。
●まとめ
自律神経は私たちの健康を支える大切な働きを担っています。しかし、ストレスや生活習慣の乱れによってバランスを崩すと、心身に様々な不調を引き起こします。
「最近、疲れが取れない」「気分が落ち込みやすい」と感じる方は、自律神経の乱れが原因かもしれません。
次回のブログでは、自律神経の乱れによって現れる具体的な症状をさらに詳しくご紹介します。
PDFはこちら