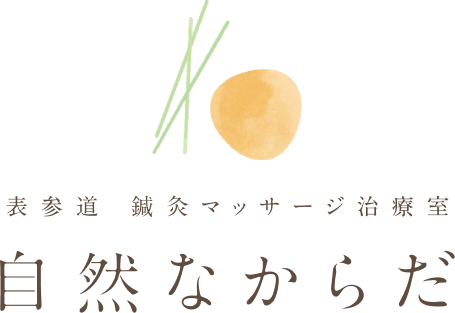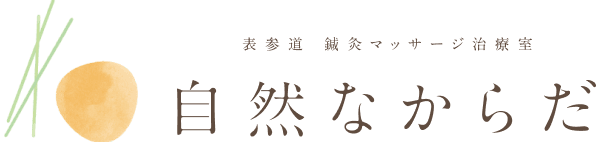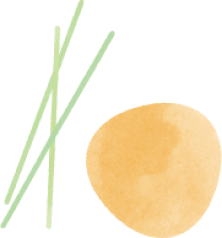新着情報

(3)なぜストレスで自律神経は乱れるのか|東洋医学からの視点
ストレスと自律神経

●はじめに
「ストレスがたまると体調が崩れる」「気持ちが落ち込むと疲れやすい」――誰もが一度は経験したことがあるはずです。この背景には、自律神経の乱れがあります。
今回は、なぜストレスが自律神経に影響を与えるのかを、西洋医学と東洋医学の両面から解説します。
●西洋医学から見たストレスと自律神経
私たちの体はストレスを感じると、脳が「危険」と判断し、交感神経を活発に働かせます。交感神経は「戦う・逃げる」ためのモードをつかさどり、心拍数を上げ、筋肉を緊張させ、血圧を上げます。
本来なら、ストレスが去れば副交感神経が働いて体を休ませてくれます。
しかし、現代社会では仕事や人間関係など慢性的なストレスが続くため、交感神経が休まらず緊張状態が長引くのです。
その結果、
・疲労感が取れない
・気分が不安定になる
・胃腸の不調が続く
・頭痛や肩こりが慢性化する
といった症状が現れてきます。
●東洋医学から見たストレスと気血の巡り
東洋医学では、ストレスによる不調を「身体の巡りが悪くなる状態」と考えます。イライラ → 肝(かん)の働きが乱れ、気の巡りが滞る
気分の落ち込み → 気が不足し、心身が弱る
胃腸の不調 → 気の停滞が消化吸収の働きを妨げる
つまり、ストレスは単なる「気持ちの問題」ではなく、体内の巡りや臓器の働きを乱す大きな要因と考えられてきました。
●鍼灸でできるサポート
鍼灸では、ストレスで過緊張になった交感神経をやわらげ、副交感神経が働きやすい状態を作ります。特に「百会(ひゃくえ)」「内関(ないかん)」などのツボを用いて、頭や胸の緊張を和らげ、全身の巡りを改善します。
●ツボの位置
(1)百会(ひゃくえ)
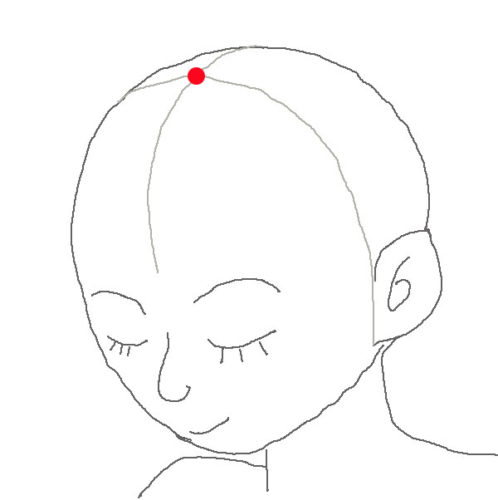
耳の付け根の上下を結んだ線と、身体の中心(鼻を通る縦の線)が交わるところ。
(2)内関
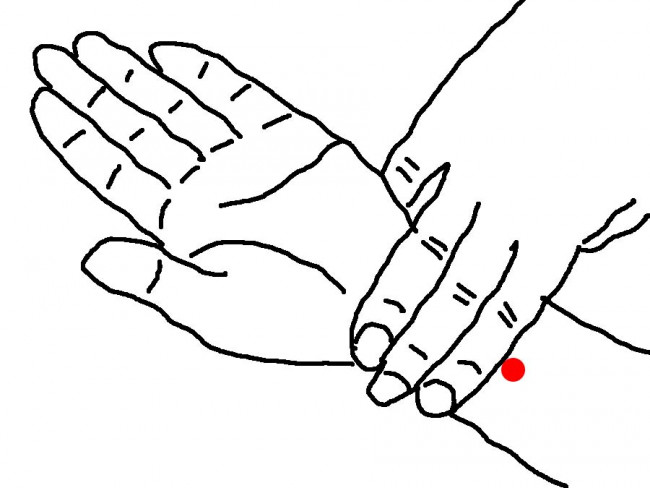
手首の関節から指3本分、腕の幅の丁度中間の位置にとるとよいです。
(3)ツボの押し方
セルフケアの場合は、「ツボの位置を軽く10回押したら少し休む」を3セットぐらいやって
みて下さい。
治療の場合にはこのツボの位置に鍼をしたり、お灸をしたりします。
実際に患者さんからは、
「気持ちが落ち着き、よく眠れるようになった」
「疲れがたまりにくくなった」
「胃腸の調子が良くなった」
といった声をいただいています。
●まとめ
ストレスは避けることができなくても、その影響を小さくすることは可能です。西洋医学的にも東洋医学的にも、ストレスは自律神経を乱し、心身にさまざまな不調をもたらします。
表参道の鍼灸院「自然なからだ」では、やさしい鍼灸で自律神経のバランスを整え、ストレスによる不調改善をサポートしています。
PDFはこちら